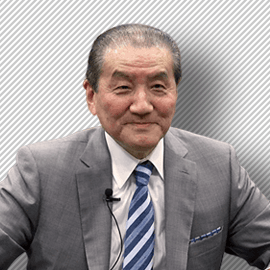公武統一政権を作った秀吉の狙いとその歴史的意味
豊臣兄弟~秀吉と秀長の実像に迫る(9)秀吉が作った公武統一政権と歴史のif
秀吉は室町時代までとは全く違う武家政権を作ってしまったという黒田氏。それが「公武統一政権」で、これは江戸時代にも受け継がれなかったため、日本史の中で唯一のことである。いったいどういうことなのか。また、なぜ江戸幕...
収録日:2025/10/20
追加日:2026/02/01
人生はエネルゲイア――AIにない「自分と出会うチャンス」
AI時代と人間の再定義(4)自分と出会うチャンス
書くという行為は自分と出会うチャンスである。そう考える中島氏は、書くという行為をダンスに喩え、単に踊って終わりという目的達成のためではなく、いつどこで踊り終えてもいいそのプロセス自体が貴重なプロセスだという。で...
収録日:2025/07/12
追加日:2026/01/31
耳障りな言葉がポイント!?新しい概念を生み出すチャンス
AI時代と人間の再定義(3)Human Co-becomingと存在神学への対抗
人間が成すべき知的営みとは、“言語に無理強いをする”ことによって新しい概念を生み出して世界の見え方そのものを更新していくことだという中島氏。そこで「Human Co-becoming」、すなわち他者や環境との関わりの中で人間的にな...
収録日:2025/07/12
追加日:2026/01/30
厳しい修行の禅が日本に残ったのは武士道と合一したから
日本文化の世界的特徴(7)死ぬために座る
禅はインドから中国を経由して日本に伝わったが、今や禅文化が残っているのは日本だけである。これは仏教と武士道と合一したからだと執行氏は言う。武士道は野蛮性と高貴性を備えた文化だが、それと合一したことで、座禅は死に...
収録日:2025/10/23
追加日:2026/01/30
利益か社会課題解決か…かつての日本企業の美点を取り戻せ
これからの社会・経済の構造変化(2)経済的利益と社会課題解決の両立へ
日本にはもう一つ大きな課題がある。経済的利益と社会課題の解決を両立できるのかという課題だ。そこで注目を集めているのが、「ステークホルダー資本主義」と呼ばれる考え方である。自社の利益だけでなく、従業員を大事にし、...
収録日:2025/12/09
追加日:2026/01/29
フラット化…日本のヒエラルキーや無謬性の原則は遅すぎる
これからの社会・経済の構造変化(1)民主主義と意思決定スピード
いま世界が大きな転換期を迎えている。これから日本社会と経済の構造も大きく変わっていくことは間違いない。では、どのように変わっていくのか。柳川範之先生が、そのヒントを鋭く探っていく講義シリーズ。インターネットやAI...
収録日:2025/12/09
追加日:2026/01/28
科学は嫌われる!? なぜ「物語」のほうが重要視されるのか
「進化」への誤解…本当は何か?(9)AI時代の人間と科学の関係
AI時代に人はその技術とどう付き合っていくべきか。そして、われわれはAIからの情報を本当に「信じる」ことができるのか。また、人々が「物語」を求める中で、科学がやるべきことは何なのか。聴講者との質疑応答を通じて考える...
収録日:2025/05/17
追加日:2026/01/27
なぜ変異が必要なのか…現代にも通じる多様性創出の原理
「進化」への誤解…本当は何か?(8)偶然の進化と多様性創出の原理
科学的な思考を社会思想と分けて考えることは難しい。その背景には、「ただの偶然」で世界を説明されることの受け入れ難さがあるのかもしれない。科学的な説明を「ただの偶然」として理解することの意義や、生物における多様性...
収録日:2025/05/17
追加日:2026/01/26
適者生存ではない…進化論とスペンサーの社会進化論は別物
「進化」への誤解…本当は何か?(7)進歩思想としての進化論と社会進化論
ダーウィンの進化論は、生物の目的や社会の発展といった進歩思想とは区別された、純粋な科学的理論構築として取り組まれていた。しかし、ダーウィンの理論を受け入れ、広めた多くは進歩思想を支持する人々だった。進歩思想に「...
収録日:2025/05/17
追加日:2026/01/26
「家康対奉行」の構図は真っ赤な嘘!? 秀吉政権瓦解の真相
豊臣兄弟~秀吉と秀長の実像に迫る(8)秀長の死の影響と秀吉政権の瓦解
天正19(1591)年、秀吉は子の鶴松と秀長が相次いで死去し、関白職を甥・秀次に譲り、太閤と呼ばれるようになる。これ以降、羽柴(豊臣)政権は迷走し、やがて崩壊へと向かうことになるが、それゆえ秀長の存在感が没後、よりク...
収録日:2025/10/20
追加日:2026/01/25
仏法僧の三宝――なぜ1人で仏教に向かってはいけないのか
AI時代と人間の再定義(2)仏法僧の三宝と対話による道徳的進歩
「仏法僧の三宝を敬いなさい」という仏教の教えがある。中でも問題なのは僧、つまり人である。思考は1人で行うものではなく、人と人との対話を通じて行う共同行為で発見的プロセスである。つまり、1人では妄想に陥る危険がある...
収録日:2025/07/12
追加日:2026/01/24
AIは間違いが分からない…思考で大事なのは訂正可能性
AI時代と人間の再定義(1)AIは思考するのか
AIは考えているのか、考えていないのか――この問いについて議論する前に、そもそも「考える」とは何なのかという大問題がある。この問題について、マルクス・ガブリエル氏は身体と結びつけて「考覚」という表現で考えている。で...
収録日:2025/07/12
追加日:2026/01/23
「御稜威の力」こそが敗戦国として占領された日本を救った
日本文化の世界的特徴(6)「御稜威の力」とは何か
戦後の憲法をGHQがつくったからと憎んでいる日本人もいるが、そう考えているあいだは、日本から世界をリードする文化を築くことはできないと執行氏は言う。敗戦後、日本の庶民は占領軍司令官のマッカーサーを「格好いい」と言い...
収録日:2025/10/23
追加日:2026/01/23
江戸時代の歌舞伎にも大波乱が…どうやって生き残ったか
歌舞伎はスゴイ(4)歌舞伎のサバイバル術(後編)
江戸時代を通して歌舞伎が人々の注目を集めていたわけではなく、人形浄瑠璃をはじめ人気の娯楽が数々出てきて、歌舞伎の人気が落ちていく局面も幾度もあった。しかしそこで様々な工夫によって、人気を取り戻し、多くのお客様を...
収録日:2019/04/03
追加日:2026/01/22
草創期からの度重なる「規制」と「スキャンダル」を超えて
歌舞伎はスゴイ(3)歌舞伎のサバイバル術(前編)
一般的には、「江戸時代は歌舞伎がずっと人気だったのではないか」というイメージが持たれているかもしれない。だが実は、歌舞伎の歴史そのものも、まことに波乱万丈なものであり、そこからのサバイバルを成し遂げていくもので...
収録日:2019/04/03
追加日:2026/01/21
欧州では不人気…木村資生の中立説とダーウィンとの違い
「進化」への誤解…本当は何か?(6)木村資生の中立説
ダーウィンの進化論以降、生物の進化に関する議論はどのように発展してきているのか。重要な議論として、木村資生(国立遺伝学研究所名誉教授)の中立説がある。生物の生存と繁殖に必ずしも関連しない、分子レベルでの変異を計...
収録日:2025/05/17
追加日:2026/01/20
ダーウィン「進化論」執筆の背景…娘の死と信仰との決別
「進化」への誤解…本当は何か?(5)ダーウィンの生物紀行
進化の理論を科学的に突き詰めようとしたダーウィン。その背景には、昆虫少年だった幼少期と若くして世界をめぐり生物の多様性を目の当たりにした経験があった。ダーウィンの生い立ちと生涯から、その探究の源泉を探る。(2025...
収録日:2025/05/17
追加日:2026/01/19
想像以上に有能――領民に慕われた秀長のリーダーシップ
豊臣兄弟~秀吉と秀長の実像に迫る(7)領国経営と秀長の統治能力
秀長は領国大名としてセオリー通りの統治を行い、領民にも慕われたという史料が残っている。そのリーダーシップは家来や領民への統制に長けていたことが新たな研究により分かったが、秀長が想像以上に有能だったことは間違いな...
収録日:2025/10/20
追加日:2026/01/18
ナイチンゲールの怒りから学ぶこと…逆境の中で考えるとは
逆境に対峙する哲学(10)遺産を交換する
台本もない。主語もない。専門分野も違う。3人の哲学者による2時間におよぶ「哲学カフェ」風鼎談講義は筋書きのない世界をさまよいながら、いよいよ最終回を迎えることに。カルヴィーノ、ナイチンゲール、本居宣長、プラトンの...
収録日:2025/07/24
追加日:2026/01/17
本居宣長も白隠もハイデガーも友となる――大切なのは?
逆境に対峙する哲学(9)先人の知恵という友
人生に逆境はつきものだが、その中でわれわれは変化し成長していく。そこで大切なのは、これまで話題になってきた本居宣長や白隠やモンテーニュなど、先人たちが何を考えどう生きてきたかを知識として知ることだ。彼らの知識を...
収録日:2025/07/24
追加日:2026/01/16
天皇は神話と現実が同一化されている「目に見える象徴」
日本文化の世界的特徴(5)神話から現世への連続性
これまで世界でさまざまな王朝が生まれたが、ここまで長きにわたって、現代に至るまで続いているのは日本の天皇だけである。126代続いたのも大変なことで、天皇は日本だけでなく「世界の宝」とさえいえる。天皇制の特徴は神話と...
収録日:2025/10/23
追加日:2026/01/16
歌舞伎十八番を定めた七代目市川團十郎、一番モテた八代目
歌舞伎はスゴイ(2)市川團十郎の何がスゴイか(後編)
第2話では七代目と八代目の市川團十郎に光を当てる。七代目は寛政3年(1791年)に生まれて安政6年(1859)に亡くなっており、八代目は文政6年(1823年)に生まれ、嘉永7年(1854年)に亡くなっている。江戸後期から幕末にかけて...
収録日:2019/04/03
追加日:2026/01/15
市川團十郎の歴史…圧倒的才能の初代から六代目までの奮闘
歌舞伎はスゴイ(1)市川團十郎の何がスゴイか(前編)
江戸の歌舞伎の歴史をひもときながら、その魅力に迫っていく講義シリーズ。まず第1話と第2話で歴代・市川團十郎の事績をたどって「江戸で歌舞伎がいかに発展していったか」を探り、そして第3話と第4話で「いかに歌舞伎がたくま...
収録日:2019/04/03
追加日:2026/01/14
『種の起源』…ダーウィンとウォレスの自然淘汰の理論
「進化」への誤解…本当は何か?(4)ダーウィンの進化論と自然淘汰の理論
進化論といえばダーウィンだが、彼の有名な著作『種の起源』の出版には、ラッセル・ウォレスという人物をめぐる想定外の事態があった。科学的進化論の端緒である『種の起源』誕生の背景と、その議論のポイントについて解説する...
収録日:2025/05/17
追加日:2026/01/13
ラマルクの進化論…使えば器官が発達し、それが子に伝わる
「進化」への誤解…本当は何か?(3)進化学説史と近代の生物実験
古代ギリシアから議論されてきた生物の発生や進化の問題は、近代に入り実験的に検証されていくようになる。今回は、フランチェスコ・レディ、フランシス・ベーコン、カール・フォン・リンネといった学者たちの探究について解説...
収録日:2025/05/17
追加日:2026/01/12
文武両道の名将…大大名たちを魅了した秀長の器量とは?
豊臣兄弟~秀吉と秀長の実像に迫る(6)秀吉との信頼関係と秀長の軍事能力
「補佐役」としての秀長の真骨頂は外交力だったといわれるが、軍事力においても秀吉が全面的に信頼を寄せる、優れた力量の持ち主だった。その二つを惜しみなく発揮したことが、秀吉の天下一統を成功させたのだろう。「文武両道...
収録日:2025/10/20
追加日:2026/01/11
宮本武蔵「型を捨てろ」と「守破離」が教えてくれること
逆境に対峙する哲学(8)白隠の覚悟
18世紀の禅僧・白隠は画を用いて各地で民衆を教化した。民間への浸透ぶりを伝える逸話の一つに赤ん坊をめぐる話がある。修行を積んだ禅僧ですら予期しない逆境に出会う。エスカレートしていく状況のいちいちに彼は「ああ、そう...
収録日:2025/07/24
追加日:2026/01/10
モンテーニュの告白「学が邪魔をすることがある」と百姓の力
逆境に対峙する哲学(7)試練と祟りと弱さの力
西洋では逆境を神からの「試練」と捉えたが、神道では「祟り」と捉える。祟りに対しては下手の考え休むに似たり、儀式の中で和解するしかない。16世紀の哲学者モンテーニュは、ペストの流行や宗教戦争の中、たくましく生きる百...
収録日:2025/07/24
追加日:2026/01/09
中国語を「日本語で読める」ようにした漢文訓読の凄さ
日本文化の世界的特徴(4)漢文訓読の力
中国語を日本語で読めるようにした「漢文教育」は日本人の途轍もない発明である。日本はかつて中国文明を取り入れるために中国の文献から学ぶ際に、中国語で読むのではなく、訓読できるように返り点などの工夫を重ねた。これは...
収録日:2025/10/23
追加日:2026/01/09
戦略的資本主義とは?日本再生へアメリカに学ぶ5つの提言
戦略的資本主義と日本~アメリカの復活に学ぶ5つの提言
「戦略的資本主義」は、市場原理を尊重しつつ国の長期的な競争力強化に重点を置く経済体制を指す言葉だ。日本研究に取り組んだアメリカの学者が戦後日本経済の発展を説明する概念として、20世紀末に提唱している。その後の米中...
収録日:2025/11/10
追加日:2026/01/08