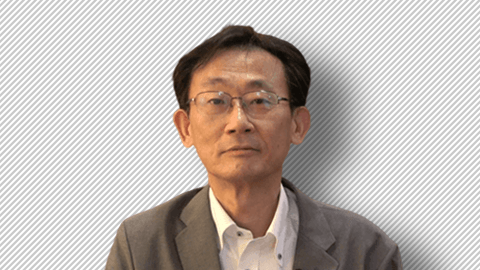<プロフィール>
1959年福岡県生まれ。
【学位】
博士(文学)(広島大学文学部) 【2002年取得】
【学歴】
広島大学文学部史学科(考古学専攻) 【1981年卒業】
九州大学大学院文学研究科考古学専攻博士後期課程 【1986年単位取得退学】
【職歴】
1986年 九州大学文学部助手
1988年 国立歴史民俗博物館考古研究部助手
1999年 国立歴史民俗博物館歴史研究部助教授
2003年4月 総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻助教授併任
2007年4月 大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授
2007年4月 総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻准教授併任
2008年11月 大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部教授
2009年4月 総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任
【専門分野】
先史考古学
【主な著書】
『新弥生時代』(吉川歴史文化ライブラリー329,吉川弘文館,2011年10月)
『弥生文化像の新構築』(吉川弘文館,2013年5月)
『弥生時代の歴史』講談社現代新書(2015.5月)
『弥生時代って、どんな時代だったのか?』(藤尾編 朝倉書店、2017年3月)
『ここが変わる!日本の考古学』(松木武彦と共編著 吉川弘文館、2019年3月)