
山上憶良「沈痾自哀文」と東洋的死生観 (全4話)

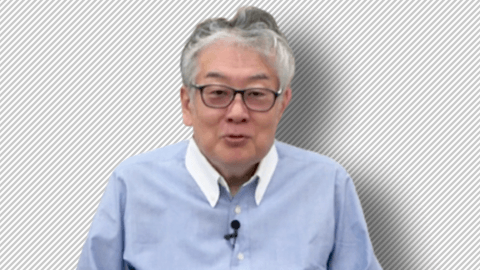
うえのまこと

山上憶良「沈痾自哀文」と東洋的死生観 (全4話)

山上憶良「好去好来の歌」を読む (全4話)

万葉集の秘密~日本文化と中国文化 (全5話)

折口信夫が語った日本文化の核心 (全4話)

ソフトな歴史学のすすめ (全5話)

「万葉集」の聖徳太子――語りかける人 (全6話)